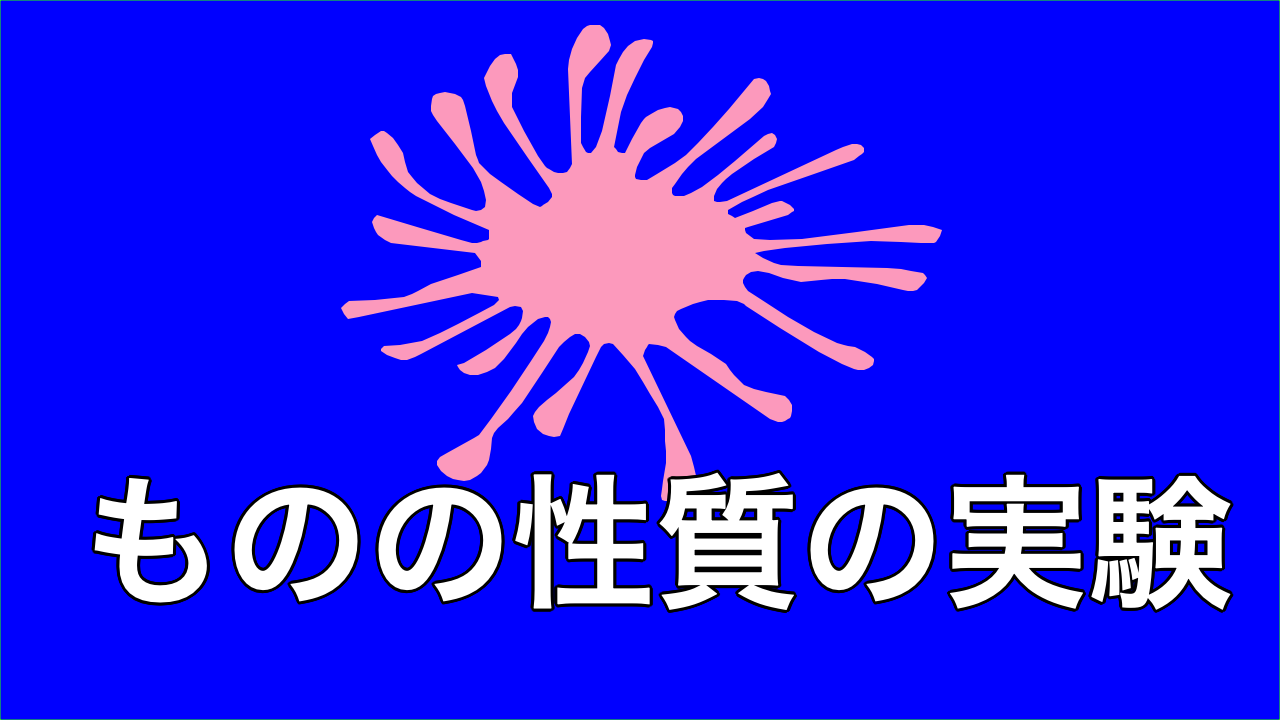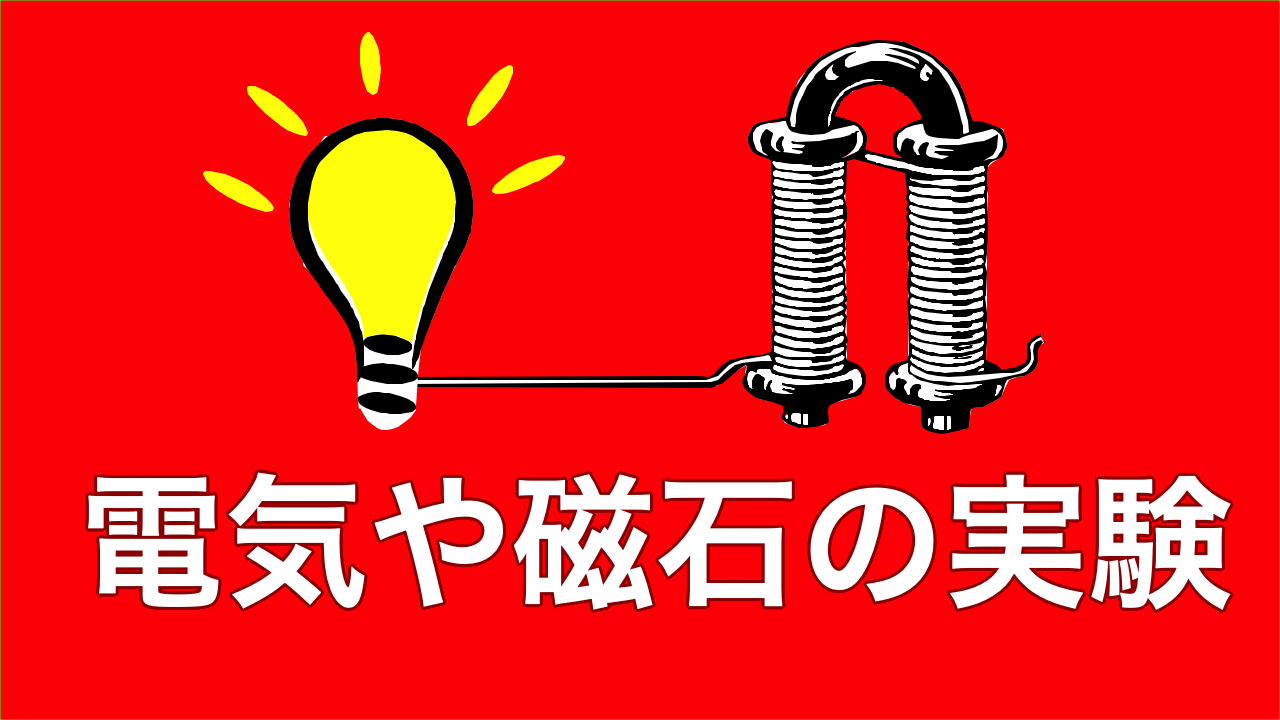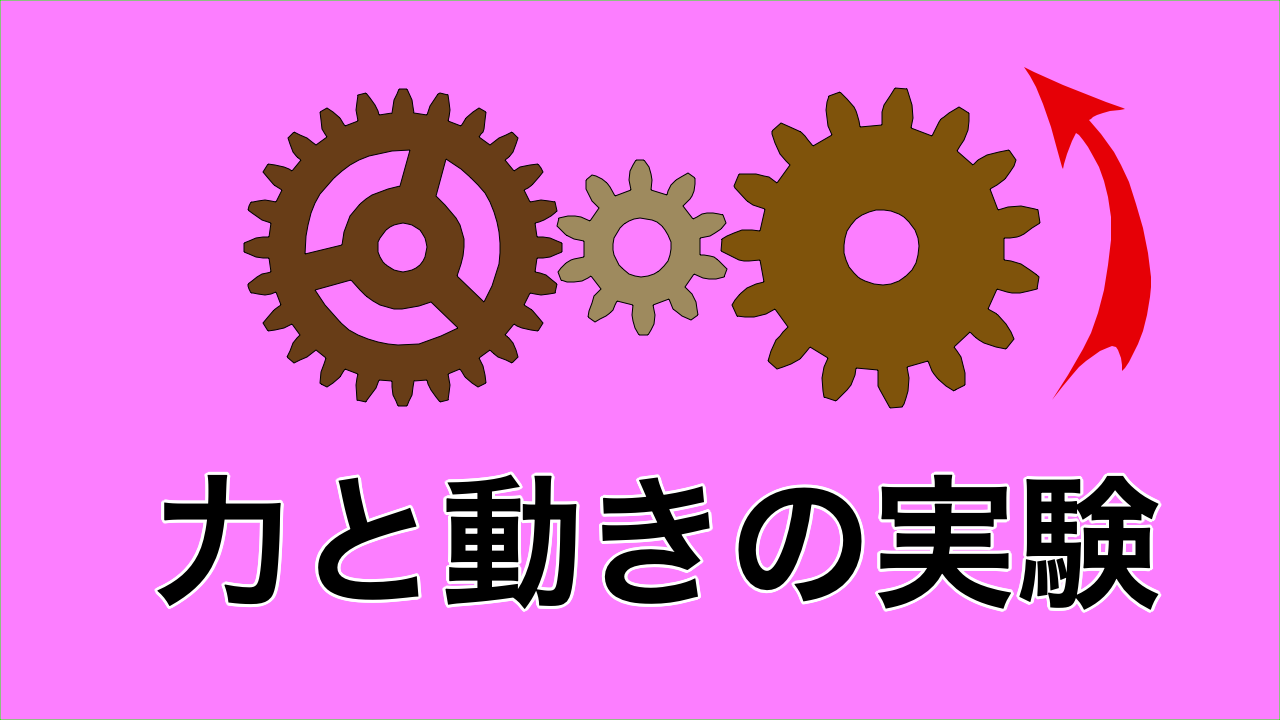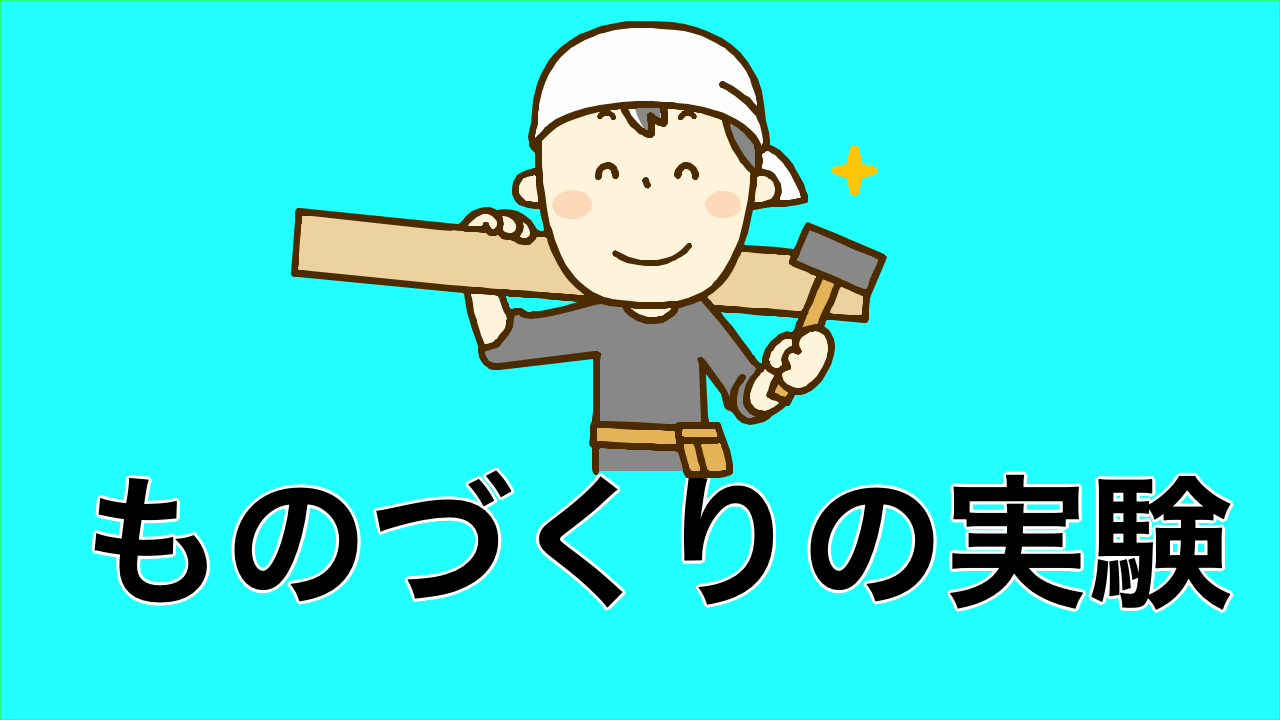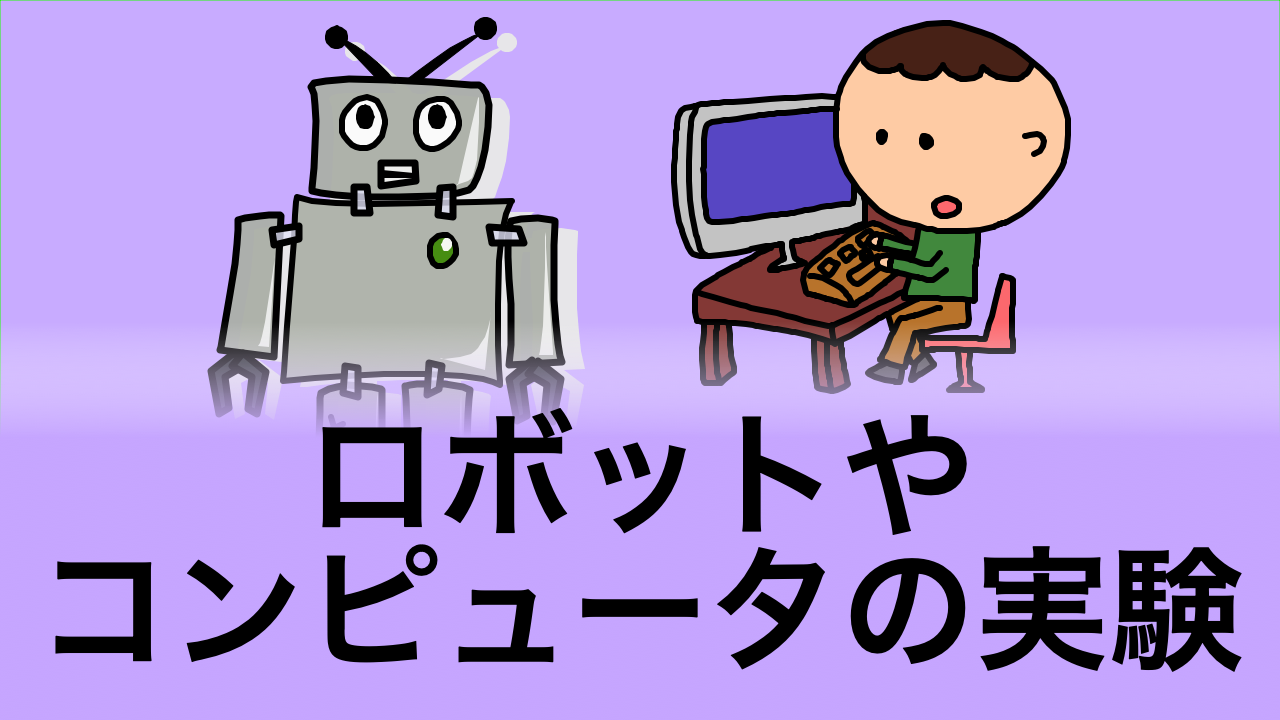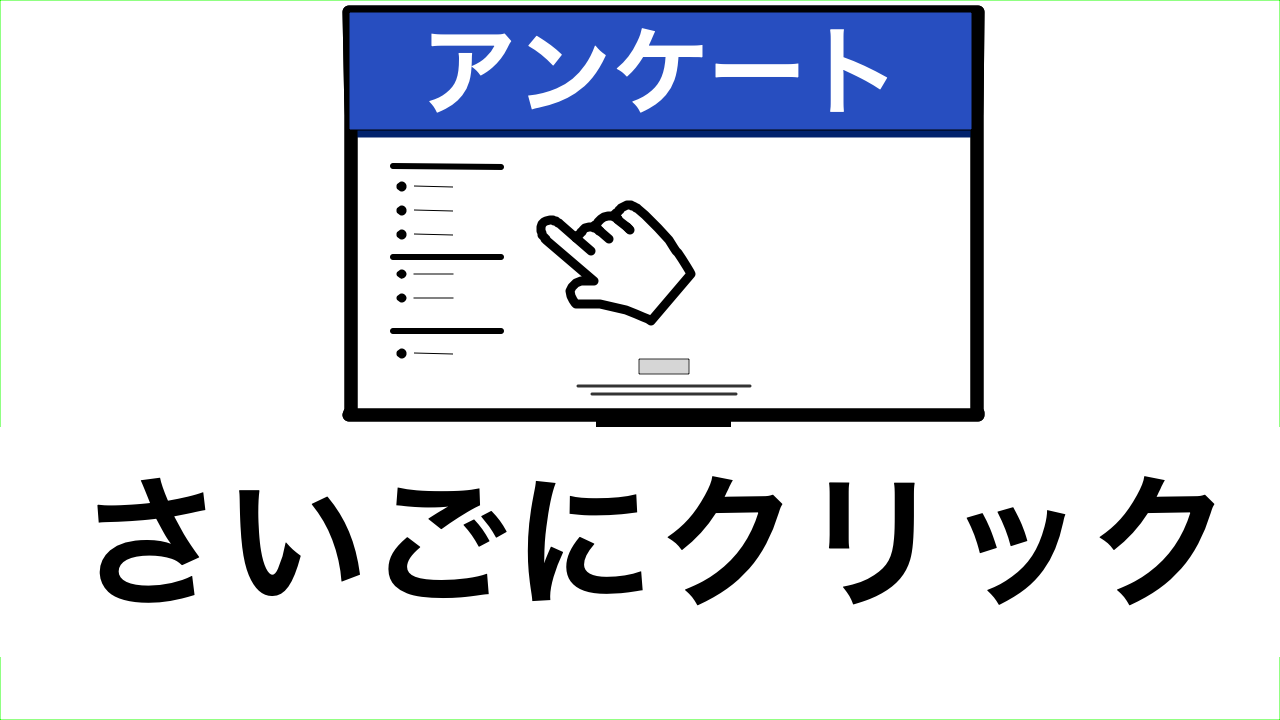ガイドブック
第30回 青少年のための科学の祭典 大阪大会
子どもと青少年の創造力と適応力を育む科学実験と工作教室
全Webブース 一覧
Web開催となった今年は,それぞれの出展者が実験動画を作成しました。たくさんの「Webブース」から,「ガイドブック」や「実験動画」をご覧ください!
11. 風がないのにまわりだす!? 不思議な風車
コップをかぶせることで、風を送っているわけでもないのに、折り紙で作った風車がゆっくりとくるくる回りだします。風車を回しているのは何者なのでしょうか・・・。それは自分の手から発せられている、あるものなのです。...
PDFでご覧いただけます
12. カメラのしくみ
今では携帯電話やスマートホンにもついているカメラ。手軽に写真が撮れて、プリントアウトしたり、ネット上で誰でも簡単に見たりすることができます。このカメラは、1839年にルイ・ダゲールという人が発明したダゲレオタイプと呼ばれるものが最初だと言われています。カメラの原理は、凸レンズを用いて光を集め、像を作ることです。できた像...
PDFでご覧いただけます
13. 鏡の中のふしぎな世界
多くの人が毎日使う鏡。その使い方は、ただ身だしなみを整えるだけではありません。使い方を変えることで様々な科学の発見ができます。そんな鏡の知られざる世界を見てみましょう!...
PDFでご覧いただけます
14. 不思議なシャボン膜
シャボン玉はどんな形をしていますか。きれいな球形をしていますね。なぜでしょうか。四角の枠にできるシャボン膜は平らな面になっていますね。なぜでしょうか。シャボン膜を作る枠が立方体や正四面体ではシャボン膜はどのような形になるでしょうか。試してみましょう。...
PDFでご覧いただけます
15. 混ざった色を分けてみよう!
皆さんは絵の具などで色を混ぜたことはありますか。複数の色を混ぜることでまったく新しい色ができあがりますよね。そんな混ざった色を分けてみたいと思ったことはありませんか?水を使って簡単に色を分けることができます!...
PDFでご覧いただけます
16. 光と色をカガクする
私たちは、朝が来たら太陽が昇り、あたりは明るくなり、夜になって暗くなると照明器具を使います。このことは普段当たり前すぎて、「光」について、考えることは少ないのではないでしょうか。また、「リンゴはなぜ赤い」「空はなぜ青い」など、「色」についてじっくりと考えたことがあるでしょうか。今回は、水性ペンと偏光板を使って「光」と「...
PDFでご覧いただけます
17. 自分で紙をつくってみよう!
普段何気なく使っている「紙」が、どうやってつくられているのか知っていますか?日本の和紙は、昔から「コウゾ」「ミツマタ」「ガンピ」などの木の皮の部分を使って作られています。昔ながらの紙づくりを体験することで、物を大切にする気持ちや、使う人、作る人の責任、人の暮らしと自然の関係などを考えてみましょう。...
PDFでご覧いただけます
19. 梅田で化石・鉱物を観察しよう
ワンダーちがく
都会のビルの壁には多くの石材が使われています。ビルの石材にはアンモナイトなどの化石やガーネットなどの鉱物も含まれています。都会の化石探検に出かけましょう!...
PDFでご覧いただけます
20. 虹をもって歩こう!!Ⅲ -分光と偏光-
理科の地学では、光を使った実験や観察があります。七色の虹は空にかかる気象現象ですし、岩石を薄く削って偏光板で見ると岩石の中の鉱物は、万華鏡のように色が変わります。このブースでは、虹がどうして七色に見えるのかや、石がどうして万華鏡のように見えるのか、それから石の何がわかるのかについて実際に石を見ていただきながらお話します...
PDFでご覧いただけます
(2021年大会)

(2021年大会)


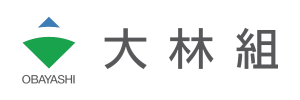




(2021年大会 特別協力)
(2021年大会 特別協力)
- 「青少年のための科学の祭典」
大阪大会実行委員会 - 日本物理教育学会
近畿支部 - 一般社団法人
日本物理学会大阪支部 - 大阪市立科学館
- 関西
サイエンス・フォーラム - 読売新聞社